保育施設向け・事業者さま向け「こども誰でも通園制度」
まるわかりガイド
2026年から本格化される
「こども誰でも通園制度」。
本ページでは、制度の活用に向けて
検討を初めている保育施設さまへ、
制度についての説明や活用するための
ポイントをまとめてご紹介します。
こども誰でも通園制度ってどんな制度?
こども誰でも通園制度は、令和5年6月に「こども未来戦略方針」の中で打ち出され、
令和8年度(2026年度)からの本格的な制度化に向けて、現在は「試行的事業」として多くの自治体や保育施設で実施されており、
実施状況を踏まえながら制度内容の検討や体制づくりが進められています。
制度の主な目的

-
01
すべての子どもの育ちを応援し、
良質な成育環境を整備すること -
02
すべての子育て家庭に対して、多様な働き方や
ライフスタイルにかかわらず
支援を強化すること -
03
0歳から2歳の未就園児を含め、
孤立した育児による不安や悩みを
抱える家庭を支援すること
こども誰でも通園制度は、保育所等に通っていない子どもたちが保育所等で過ごす機会を保障し、支援していくという点で、従来の保育における大きな転換点となります。
令和7年度には、児童福祉法において「乳児等通園支援事業」として位置づけられます。 また、子ども・子育て支援法においては、地域子ども・子育て支援事業の一つとして実施され、令和8年度以降は「乳児等のための支援給付」として全国で実施される給付制度となる予定です。
令和8年度の本格実施に向けては、給付制度として全国で実施されること、利用可能時間を法令上規定する必要があること、1時間当たりの費用について公定価格として設定する必要があること、従事者向けの研修を開発し安全性や専門性を担保する必要があること、市町村は居住者以外の需要も考慮して提供体制を整備する必要があることなどが今も検討されています。
一時預かり保育との違い
一時預かり事業とこども誰でも通園制度の違いについて説明します。
こども誰でも通園制度と一時預かり事業は、どちらも子育て支援を目的としていますが、制度の目的、対象、実施主体、利用方法などに違いがあります。
制度を利用する際は、施設の目的や体制にあった制度を選択することが必要です。
| こども誰でも通園制度 | 一時預かり事業 | |
|---|---|---|
| 目的 | 全ての子どもの育ちを応援し、良質な成育環境を整備。家庭に対して、働き方やライフスタイルにかかわらない形で支援を強化する | 家庭における保育が困難な乳幼児を一時的に預かり、必要な保護を行うこと、および子育てに係る保護者の負担軽減を目的とする |
| 対象施設 | 保育所、認定こども園、地域型保育事業所、幼稚園、地域子育て支援拠点など | 保育所、認定こども園、地域型保育事業所、幼稚園、地域子育て支援拠点など |
| 対象となる子ども | 就労要件を問わず、保育所等に通っていない0歳6ヶ月から満3歳未満の全ての子供が対象 | 家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児 |
| 利用時間 | 1ヵ月あたり10時間の上限を想定 | 市町村ごとに設定 |
| 利用方法 | 定期利用:利用する園、曜日、時間を固定して定期的に利用する方法 自由利用:利用する園、曜日、時間を固定せず、柔軟に利用する方法 | 定期利用、自由利用など、市町村や事業者によりさまざま |
| 利用料金 | 1時間あたり300円が標準 | 自治体により異なる |
| 家庭との契約方法 | 事業者との直接契約 | 事業者との直接契約 |
| 実施形式 | 一般型(在園児と合同、または専用室独立実施型)または余裕活用型を選択 | 一般型または余裕活用型を選択 |
こども誰でも通園制度の概要
令和7年度の制度の概要は以下の通りです。
実施対象施設
● 保育所 ● 認定こども園 ● 小規模保育事業所 ● 家庭的保育事業所 ● 幼稚園 ● 地域子育て支援拠点 ● 企業主導型保育事業所 ● 認可外保育施設 ● 児童発達支援センター など
令和7年度の実施においては、対象施設が限定されておらず、認可外保育施設や専用施設においても実施されています。また、事業の実施主体である市町村から、適切に事業を実施できると認められる者に対して事業の実施を委託することができます。
対象となるこども
● 保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業等に通っていない0歳6か月~満3歳未満のこども
利用時間
● 利用者は、月一定時間までの利用可能枠の中で利用が可能。試行的事業においては、一人あたり「月10時間」を上限として実施することとされています。
利用方法
自治体、地域の実情に応じて、下記2つの利用方法から選択、または組み合わせながら実施します。
定期利用
用する園、曜日、時間などを固定して定期的に利用する方法です。 事業者にとっては利用の見通しが立てやすく、職員のシフトも組みやすいというメリットがあります。
自由利用
利用する園、曜日、時間などを固定せずに柔軟に利用する方法です。 子どもの状況や保護者のニーズに合わせて利用しやすいというメリットがあります。
実施方法
こども誰でも通園制度には、下記3つの実施方法があります。
一般型(在園児と合同)
保育施設にすでに通っている児童と一緒に保育をおこなう方法です。 子どもにとっては在園児と関わる機会も多く、社会性や情緒的な発達を促進することが期待できます。また、保育所等の定員とは関わりなく、こども誰でも通園制度の定員を自由に設定できます。
一般型(専用室独立実施)
在園児とは別の専用スペースを設けて保育をおこなう方法です。 利用する子どもに合わせた環境を確保できるので、一人ひとりの発達や特性に応じた保育が提供可能になります。また、保育所等の定員とは関わりなく、こども誰でも通園制度の定員を自由に設定できます。
余裕活用型
利用定員に達しない保育施設が、定員の範囲内で受け入れる方法です。定員の範囲内で受け入れるため、一般型と比べて職員を新たに確保する必要性も低いのが特徴です。また、受け入れ枠が時期によって変動することもあるため、同じ子どもを継続して受け入れることが難しい場合があることも留意する必要があります。
実施するのために必要な準備
こども誰でも通園制度や一時預かり保育を実施するためには、実施後に起こりうる課題への対策として、事前に保育環境や体制を整備することが大切です。
安全面の強化
不慣れな環境の中では子どもも大きなストレスを感じます。特に小さい赤ちゃんは乳幼児突然死症候群(SIDS)のリスクも考慮し、安全面を第一に考える必要性が指摘されています。誤って事故が起きてしまわないように、安全な保育環境を整えることが重要です。
職員の負担
利用者への説明や問い合わせ対応、面談業務など、制度の実施により保育者は慣れない業務を行う必要があります。そのため、職場環境や業務内容の変化に対する負荷や不安感により、保育者の心身にストレスが生じる可能性があります。保育者が保育に専念できる環境整備が必要です。
情報の共有・連絡
短時間での利用や複数の事業所利用の場合、子ども一人ひとりの特性・特徴を時間をかけて把握・理解することや、子どもの育ちを継続して記録していくことが難しくなります。そのため、保護者と保育者、または保育者同士が連絡を取り合いながら子どもの情報を共有することが大切です。
年齢と発達に応じた配慮
乳幼児の年齢や発達段階、健康状態に応じた食事の把握や提供、アレルギーやアトピーなどへの配慮が必要となります。また、保育者においても0、1、2歳児の発達特性に関する知識やスキルを持つ保育者、経験豊富な人材を配置することが望ましいとされています。
誰でも通園制度の実施にはICTの活用がおすすめ
上記でお伝えした制度の実施に伴う課題への対応として、保育施設向けのICTサービスを活用することもおすすめです。書類仕事や保護者連絡などに掛かる業務負担の軽減や安全面での強化などが実現できる上、制度の利用者だけでなく、在園するすべての子どもたちに良質な保育を提供することができます。
保育向けICTサービス「ルクミー」をチェック
-
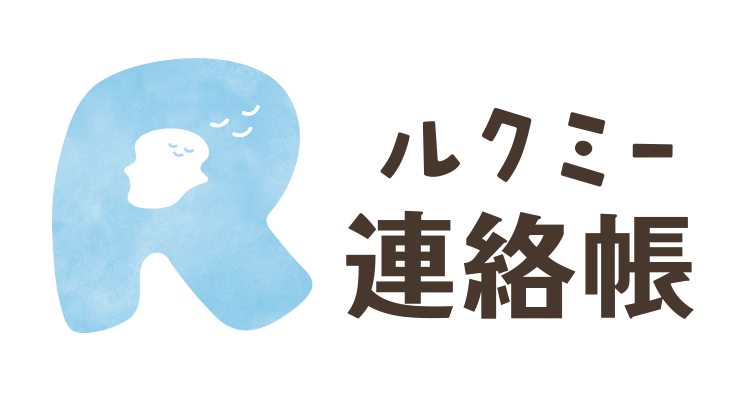
連絡帳・保護者連絡のデジタル化
手書きの負担を軽減。欠席予定や保護者からの連絡をスマートフォンでまとめて確認できます。保護者連絡も専用アプリでスムーズなやりとりが可能に。
-
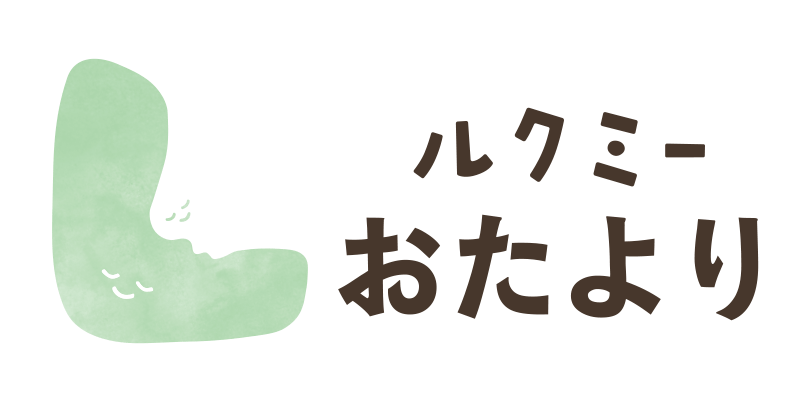
おたより・お知らせのデジタル化
おたよりやお知らせを施設全体やクラス単位で一斉配信でき、保護者の確認状況も把握できるから、伝え漏れの心配もなくなります。
-
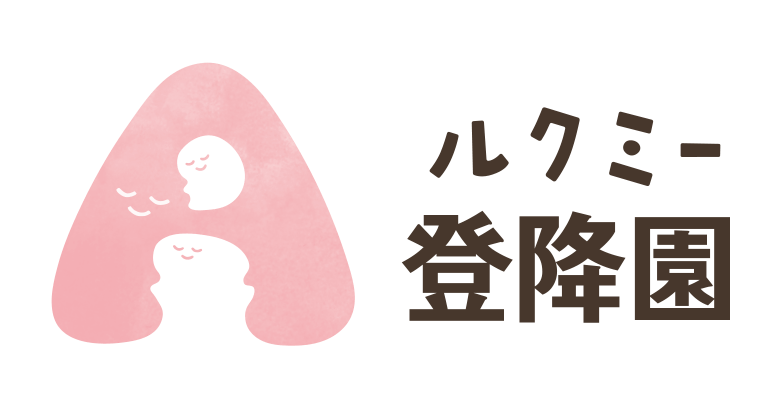
登降園アプリによる打刻管理
利用者の利用実績を集計・データ化。ルクミー請求管理にもご契約いただくと、打刻情報をもとに保育料や延長保育料も自動で集計。オムツ代やおやつ代、雑費と一緒に請求書を発行できます。
-
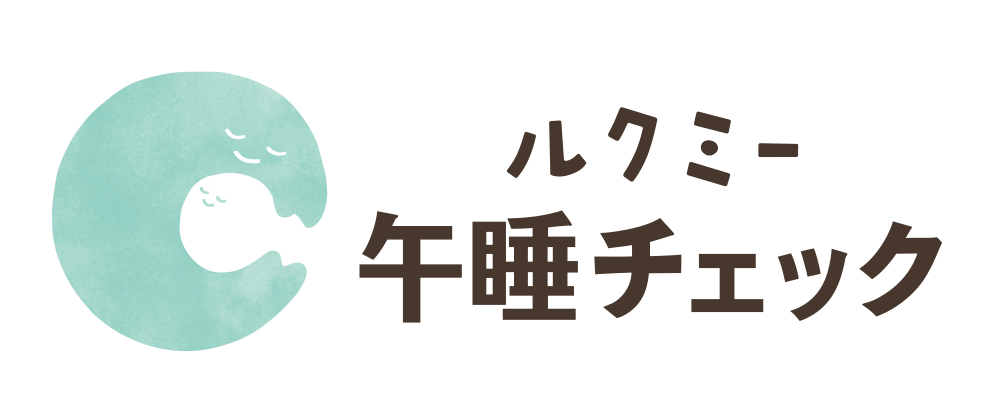
午睡センサーによる見守り強化
センサーが午睡中の体動を検知し、アプリが体の向きを自動で記録。うつ伏せ寝が続いた場合や体動静止状態が続いた場合はアラートですぐにお知らせします。
子どもともっと向き合える豊かな環境づくり。
その一歩をルクミーで始めませんか?
サービス詳細やお見積もりはもちろん、補助金利用についてのご相談、園・施設それぞれの
ご状況に合わせた導入ステップなど、まずはお気軽にご相談ください。
丁寧にご案内させていただきます。
Copyright lookmee.jp All Right Reserved.